今年で4年目となる芝浦工業大学大学院での講義『建築生産マネジメント特論』2日目を開催しました。この講義は、2022年7月に出版した書籍『現代の建築プロジェクト・マネジメント』をテキストに、執筆を担当した建設業界各分野の実務者がリレー形式で講義を行うものです。CPDS普及啓発委員長であり本書の主著者である志手一哉芝浦工大建築学部教授の授業内で開催しています。
第3講は「事業構想を評価する事業予算の計画」と題して、森トラスト株式会社発注部の山田晋治氏に、発注者の立場から建築プロジェクトの事業予算計画について講義頂きました。大手デベロッパーが“事業をやるか、やらないか”をどのように判断しているか?興味深いお話を聞かせて頂きました。
まずは不動産デベロッパーのイメージ、そして存在意義について学生に問いかけ。デベロッパーへの就職を希望する学生は2,3名と出席者の1割程度でした。
そして企画設計にあたり確認すべき事項、確認方法について解説。所在地・地番など敷地に関する情報、都市計画など法的制約や建物スペックの社内基準を踏まえた建築用途までが企画設計時に確認すること、決定することとなります。規格図を作成したら、各エリアの面積を把握し、費用想定・収入想定に繋げていきます。
続いて費用及び収入の想定。不動産開発費用(WLC)はLCC=ライフサイクルコスト(イニシャルコスト+ランニングコスト)と非建設費用から構成されます。収入は事業の種目によって販売収入、賃貸収入および営業収入に大別されます。収入から費用を除したものが利益となりますが、償却前利益と償却後利益の考え方があります。
費用対効果(=投資判断)の指標には、耳慣れない横文字でPBP、ROI、PV、NPVそしてIRRなど様々な方法があります。ひとつひとつ定義と算出方法を解説してくれました。そして不動産の価値を求める指標としての「費用対効果」について。収益還元法で求められる利回りは不動産市場の好況を受け近年下がってきているとのこと。
最後に事業評価の統一規格について説明した後、全体のまとめとなりました。聴講する学生から積極的に質問があり、熱心に耳を傾けている姿が印象的でした。
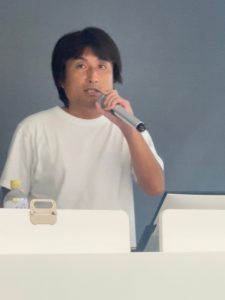
山田晋治氏
第4講「建築コストのプランニング・コストマネジメント~建築費の騰落メカニズム~」は建設総合サイト・アーキブックを主宰する弘文社の小長谷哲史氏。コストマネジメントのコンサルティングや建設市場調査業務の経験を活かして、建設事業関係者向けのウェブサイトやクラウドサービスを運営しています。
講義のはじめは「建築費の構成と算出方法」。建築費は一般的に直接工事費+共通費+消費税で構成されます。工種別、部位別の構成や建築費の算出方法を決める4つの要素①誰が、②いつ?、③目的は?、④精度は?について紹介。建築費の積算と概算の違いについても、ケーススタディを交えて解説しました。
続いて「建築プロジェクトのコストマネジメント」。プロジェクトの段階別に業務内容は異なります。適正予算設定、コスト管理、調達計画、発注・契約方法その他5つの構成要素を戦略的に使いこなすことがコストマネジメントのコツです。設計VE(=Value Engineering)のポイントや発注契約方式の選定の考え方を詳述しました。
「建築費が騰落するメカニズム」については、工事内容、市場、請負業者の能力・経験、発注・調達方式その他の5つの要因によって建築費が決まるとのこと。1980年代のバブル期、2000年代後期のリーマンショック前後そして2011年以降の震災復興期における価格騰落のメカニズムについて解説されました。
講義の最後には去年に続き、クラウドサービス「アーキブックコスト」を利用して建築費算出のデモも実施。受講した学生は一定期間サービスを無料で利用できるというプレゼント付きでした。

小長谷哲史氏
『建築生産マネジメント特論』第3日目『建築プロジェクトに求められた変化』は10月13日に開催されます。第5講はインフロニアホールディングス綿鍋宏和氏による「発注者の役割と入札契約方式の多様化」、第6講は竹中工務店の小菅健氏による「透明性確保と発注者支援への取り組み」を予定しています。受講する皆さん、乞うご期待ください。